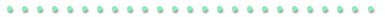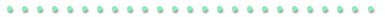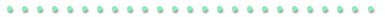大
 甲子大黒天本山は、弘法大師作の甲子大黒天を祭る日本唯一の本山です。
甲子大黒天本山は、弘法大師作の甲子大黒天を祭る日本唯一の本山です。
大黒さまのご誓願は、笑顔のなかにこそ表われています。笑顔で毎日毎日を過ごすためには、まず家族皆んなが健康であり、物質的にも十分恵まれ、しかも心に大きなゆとりをもつことが大切です。これをお授けしてくださるのが甲子(きのえね)の大黒さまです。
この『大黒さまのホームページ』を管理しているのは、甲子大黒天本山の山主です。もし希望などがありましたら、最下段のメールアドレスよりお願いいたします。
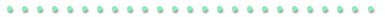 【更新情報 2026.2.15】
【更新情報 2026.2.15】
☆『ちょっとお話しを』 更新しました!
☆『小町山News』 更新しました!
☆『本のたび』 更新しました!
【最新 News 】
☆左の写真は、2月14日に撮った神殿です。
立春以降は、寒波の日もありましたが、ここ数日はこのように晴れた日が多くなり、3月なみの気温です。
現在は神殿前から入ってお参りできますが、雪が降ったりすると、暖気のときには屋根からの落選が心配され、そのような時には案内板を設置しますので、その指示にしたがって進んでくださようお願いいたします。
さて、2月の別名は、旧暦では「如月(きさらぎ)」といいますが、中国で2月の別名で使っていた漢字、「如月」をそのまま使っただけです。
でも、「きさらぎ」という言葉は日本のもので、旧暦2月でもまだ寒さが残っているから衣(きぬ)を更に着る月という意味で、「衣更着(きさらぎ)」になったのではないかと言われています。
もう一つの説は、草木の芽が張り出す月であるから「草木張月(くさきはりづき)」から「きさらぎ」になったというものもありますが、この解釈だと、春ももうすぐのような気がします。
☆右の写真は、2月12日の朝に撮った小町山自然遊歩道への道です。
前日に少し雪が降ったので、鮮明ではないのですが、この足跡からするとノウサギのようです。
この足跡を見て、子どものころにノウサギを追いかけて遊んでいたことを思い出しました。というのも、3月になると、カタ雪になり、かんじきを履かなくてもぬからなくなります。
そのようなときに、ノウサギの潜り込むような窪地を見つけて、針金を囲炉裏で目立たなくなるようになまし、そこに据え付けると、時にはかかることがあります。それを捕まえてきて、飼うのです。もちろん、エサも自分で学校帰りに野山から採ってきました。
春になると、毛の色が変わるので不思議でしたが、昔はそれぐらいノウサギがいたのです。
だから、童謡の『ふるさと』の「うさぎおいし かのやま……」というのは、まさにこのような情景を謡ったようなもので、「ウサギを追いかけたあの山」という意味だと私は思っています。
今の時代なら、動物愛護の精神から禁止されることかもしれませんが、考えてみると、私にとっては、今のネコやイヌをペットとして飼うような感覚だったような気がします。
☆左の写真は、2月13日に神殿の近くに雪洞をつくり、夕方になってから、ローソクに火を灯し、麩まんじゅうと自家製おかきを供え、さらに今年の豊作を願って俵型(出雲焼)でお抹茶をいただきました。
というのも、第49回上杉雪灯篭まつりが、2月14日から15日の両日、松が岬公園一帯で開かれるので、その気分を味わいたいと思ってつくりました。ローソクに火を灯すと、雪の中でオレンジ色に染まり、とってもあたたかく感じられます。
もともと、この上杉雪灯篭まつりは、第2次世界大戦で故郷の白い雪に想いを残しながら灼熱の南方に散った戦没者のための鎮魂祭から始まったそうで、今の時代は献灯し、恒久平和を願うことでもあります。
私の場合は、雪がたくさん降ると水不足にもならず、豊作になることを願って、水神さまを招来して願いを込めました。雪は、たしかに生活には大変かもしれませんが、それを楽しむという余裕も大切なことだと思います。
さて、「信濃三十三観音霊場の旅」も34回目になりましたが、今回は第31番札所「広福寺」で、上水内郡中条村御山里にあります。
普通は、三十三観音札所というと33ヶ所しかありませんが、信濃は善光寺の7年に1度の「善光寺前立本尊御開帳」をきっかけに始めたことで、NO.5は「善光寺」で、今までなかなかお参りする機会のなかった戸隠神社を最後に加えたので、合計で36回となりました。あと2回ですので、お付き合いください。
☆この下から、サーチエンジンGoogleによる検索ができます。ぜひ、利用ください。
連絡先 郵便番号 992-0076
山形県米沢市小野川町小町山 甲子大黒天本山
電話 0238-32-2929 Fax 0238-32-2988
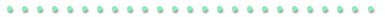 大黒さまのホームページPart2へは、下の絵馬を押して下さい。
大黒さまのホームページPart2へは、下の絵馬を押して下さい。

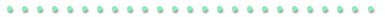 ☆リンクご希望の方は、必ずお知らせください。バナーもすぐ下に準備しておりますので、お使いください。
☆リンクご希望の方は、必ずお知らせください。バナーもすぐ下に準備しておりますので、お使いください。

Created by Yoshihiro Sekiya
Copyright(c)1998 Yoshihiro Sekiya All Rights Reserved
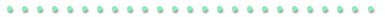
 甲子大黒天本山は、弘法大師作の甲子大黒天を祭る日本唯一の本山です。
甲子大黒天本山は、弘法大師作の甲子大黒天を祭る日本唯一の本山です。